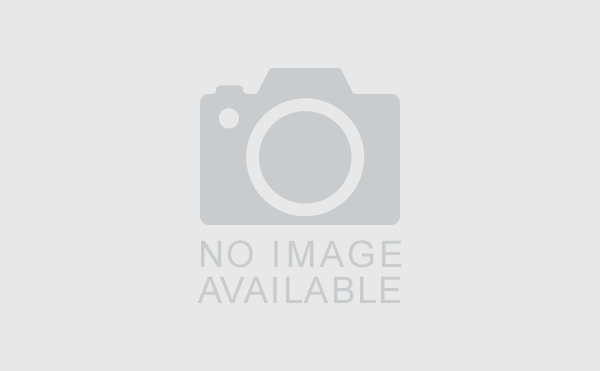“もっと早く始めていればよかった”をゼロにするために

大学入試は高校入試とは異なり、全国の受験生と競い合う厳しい挑戦です。難関大学や医学部を目指すには、日々の積み重ねと計画的な学習が欠かせません。しかし、高校1年生の段階では、大学入試の難易度や必要な準備量を十分に理解することが難しいのが現実です。

高松高校の令和7年度進学実績(学校資料)によれば、「東京大学・京都大学・大阪大学・医学部」などに現役で合格した生徒は約60名で、全体の約2割に相当します。
高松高校に限らず、どこの高校でも上位20%の生徒が学校を代表する実績を上げており、経済学でよく知られる「パレートの法則(80:20の法則)」を表しているように思います。これは、成果の多くが(8割)が一部の層(2割)に集中するというものです。学習においても、早期から計画的に取り組んだ生徒が大きな成果を上げる傾向があります。

当塾では、この“早期からの準備の重要性”を最も大切な理念の一つとしています。
生徒が「もっと早く始めていればよかった」と後悔することがないよう、高校1年生の段階から大学入試を正しく理解し、主体的に学習を進められる環境づくりを使命としています。上位20%に入れる可能性は誰にでもありますが、現実に結果を出すには早期からの準備が不可欠です。

国公立大学に合格するには、一般的に「3000時間以上」の学習が必要といわれています。これは、高校1年生の4月から毎日3時間程度の学習を継続することで達成できる水準です。難関大学や医学部を目指す場合は、さらに多くの学習時間が必要になることもあります。合否には地頭よりも「どれだけ学習時間を確保できたか」が大きく影響すると考えられています。
.jpg?resize=636%2C640&ssl=1)
高校1年生の段階では、大学入試の難易度や必要な学習量を実感しにくいことがありますが、高校3年生になると「もっと早く準備しておけばよかった」という声が聞かれることもあります。こうした経験が十分に共有されず、毎年同じ状況が繰り返されてしまうことが課題とされています。

当塾は、“生徒一人ひとりが後悔しない進路選択をできるように支える”
という理念のもと、早期からの学習支援に力を入れています。都市部と地方の学習環境の違いが話題になることもあり、より計画的な学習を促す必要があります。

香川県には「補習科」という制度がありますが、制度の有無にかかわらず、現役合格を目指して早期から計画的に学習を進めることが大切です。現役での合格可能性を高めることで、浪人という選択肢もより有効に活用できるようになります。

大学入試で後悔を残さないためには、高校1年生の段階から入試の難易度を正しく理解し、必要な準備を早めに始めることが重要です。学校や塾・予備校が協力し、生徒が将来の選択肢を広げられるよう支援していくことが求められています。